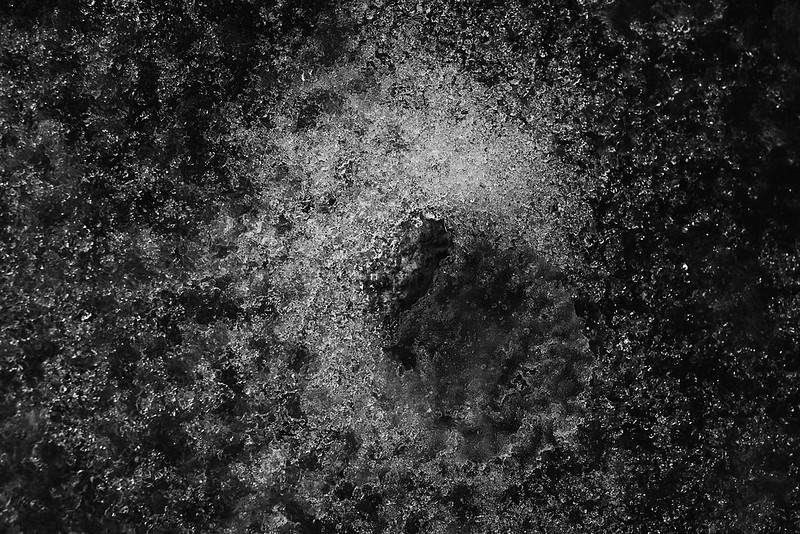赤瀬川原平の「運命の遺伝子UNA」の最後から二つ目の章「思いがけない因子のUNA」で、彼のライフワークの節目になった「トマソン」が発見されるに至った契機を彼が思い返している。「まず芸術作品への幻滅があった。作品の素材であるスクラップ類を探して、遂に廃品回収の基地であるタテバにたどりつき、山のような物品(廃品)の存在感に圧倒された。それを素材にわざわざ作品を作る行為というのが、どうにも貧弱に思われてしまった。でもそれと入れ換えに、当時前衛芸術といわれていたものが世間的に認知されて、正統的な美術館に陳列されていく。そのことのギャップがむしろ面白く、路上の工事中の穴や、横に転がる電柱や、ピカピカ点滅する明かりを、「あ、現代芸術!」といって遊びはじめた」
我々の目の鱗を落とすもっともピュアな物件としての「廃品」が、それだけで驚きの対象として完結しているにもかかわらず、わざわざ作者である私の名前を付けて社会の流通ネットワークに乗せるという行為の浅ましさやいじましさに、彼は釈然としないものを感じていたのだろう。だって、それはもう、そこにあるのだから。なぜわざわざ私の名前をそこに付けなければならないのか。それって「私の」作品? 私が作ったものじゃないのに。現代芸術というものが、かつて芸術と呼ばれていた概念を破壊するために存在するのなら、もはやそれは額縁や美術館におさまらなければならない理由はなく、芸術とさえ名付けられる必要も無く、すでに道ばたに転がっていても不思議ではない。この世界そのものが驚きの物件として存在しているのであり、宇宙の缶詰なのだ。
「人間的に観察すれば、この世の中が隅々まで人間の意図で固められたことへの嫌悪というものはあるだろう。そのような意図を逃れて、路上の無為の物件に面白さの価値を見出す。そういう因果関係はあるわけである。しかしそれは解釈のある一面であり、そのものが無為であればいいというものではない。
私たちは路上観察をおこないながら、私人個体の力では届かぬ創造の力、宗教でいう神の力の片鱗を採集して歩いているのではないかと思う。」 赤瀬川原平「芸術原論」
初期の原平さんは非常にラジカルな前衛芸術家だったけれど、その彼がなぜ路上の侘び寂び物件に価値を見出すようになったかはこの本が解き明かしてくれる。そのモチーフの一つに「意図に対する嫌悪」というものがあって、なぜ彼が意図を嫌うのかを例によって当直明けのお風呂に浸かりながらぼんやり考えていた。
ひとは意図のある作品の前では受け身にならざるを得ない。
まず始めに作者の意図がある。
作品を見る人は必然的にその意図を感じる、あるいは読み解くという立場に立たされる。
作品というものは、作品と出会った最初からそれを見るものにビハインドの立場を強いる。
それが言い過ぎなら、少なくともボールを投げるのは作者でありこちらは受け取る立場である。
原平さんはそれを生理的に暑苦しく感じたのだろう。
路上物件に作者はいない。作者の意図もない。作者も作者の意図もない作品なので、作者の意図を探らされるというビハインド感はなく、見る方にはそれをどう感じてもよいという清々しい自由がある。
現代芸術が、もうここには何も無い、ここに芸術はもとより作者も存在しないというアリバイ物件の陳列であることをやめて、芸術が通りすぎた霧箱の飛跡を発見するという意味を彼はトマソンに見出したのだろう。
そういう、受動的、能動的という視点はひとまず置くとしても「無為であればいいというものではない」とはどういう意味か。
意図というものが意識の日の当たる場所とすれば、日の当たらない無為の物件は無意識の滔々たる流れであり、原平さんというひとは何をしたひとかを一言で言えば無意識の溝(どぶ)さらいをしたひとである。
誰もが見過ごしていたどぶから面白いものを発見するひと。
どぶから引き上げた物件に名前を付けて意識の世界に投げ返すひと。
彼はもとより意識の世界の終わりに最初から立ち続けてきて、意識の終わり、その向こうは恐ろしい底なしの無意識の畔を散歩しながら、シジフォスのように無意識に向かって軽やかに網を投げ、意識のひとが無意識の海に投げ捨てたもののうちの「ほら、これ、あなたが捨てたもの」と彼から渡された物件はどれもこれも思いがけなく私たちの脳の裏側を楽しく刺激するのである。
その、彼自身の脳の裏側を通じて私たちの脳の裏側を刺激する物件を彼はとりわけ面白がった。
そしてそれがなぜ面白いのかを考え続けることで彼は自分がどこに佇んでいるかを自覚し続けたのだろう。